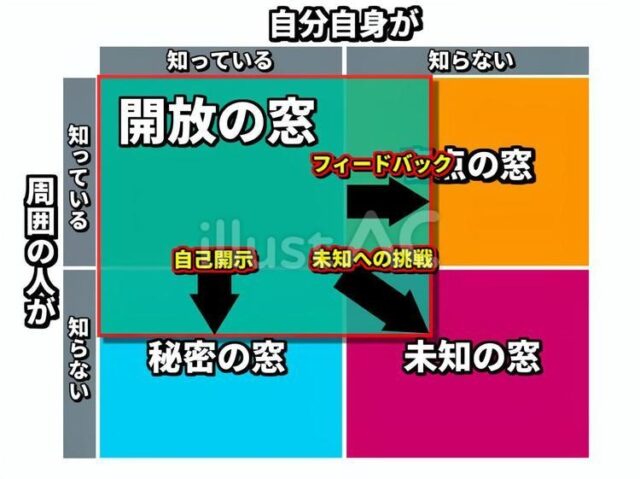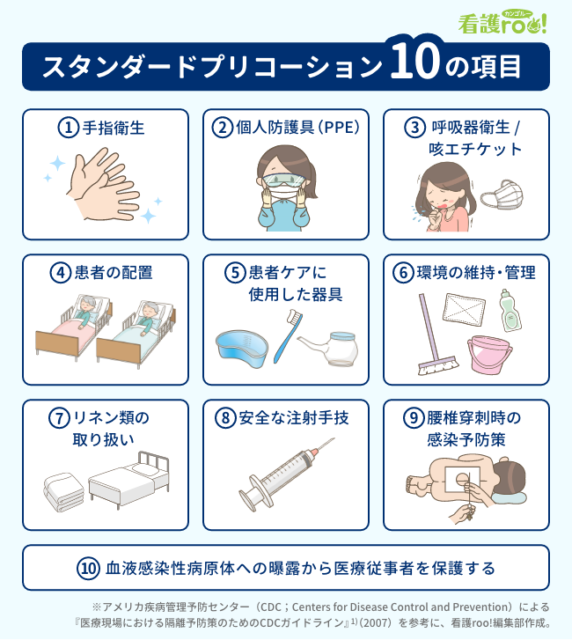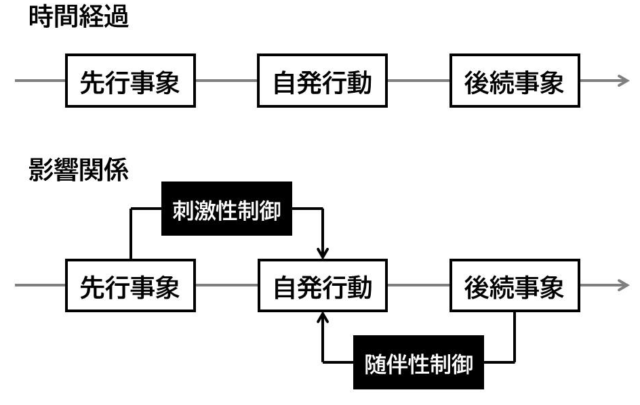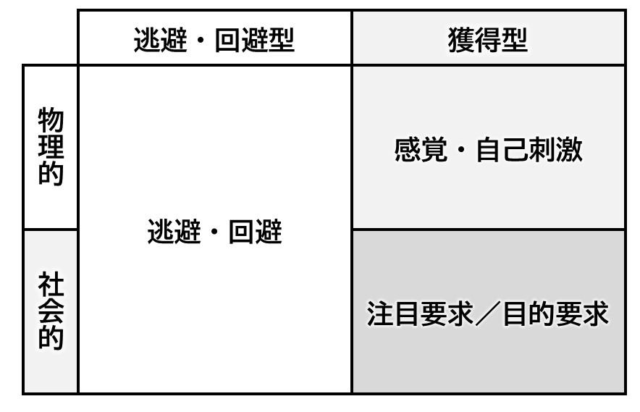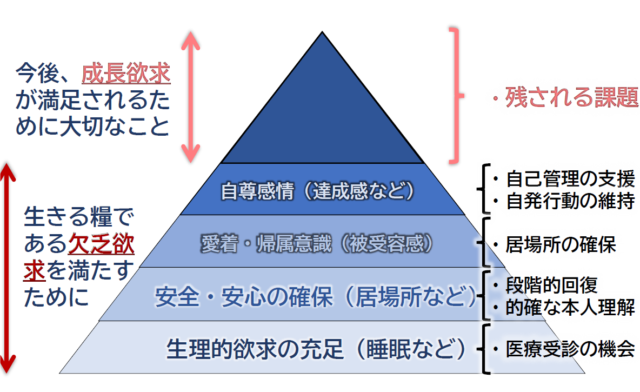●研修テーマ
プライバシー保護の取り組み
●目的
プライバシーとは何か、個人情報との違いはなにか。また、訪問介護では何がプライバシーの 侵害になるかと、
プライバシーを保護するための取り組みについて学ぶ
●内容
◎プライバシーとは
プライバシーとは「公開を望まない私的な情報」や「個人が私生活や社会行動において他人から干渉・侵害を
受けない自由」のことを指し、あくまで感受性にもとづくものでその範囲を一概に線引きすることはできないが、
基本的には、「他人に知られたくない・干渉されたくないと感じる私的領域のすべて」がプライバシーにあたると
認識する。
また、近年ではインターネットの普及・発達などにともない、「自己に関する情報をコントロールする権利
(自己情報コントロール権)」もプライバシーに含まれるとされている。
◎個人情報とは
個人情報とは生存する個人に関する情報で、氏名・生年月日・住所などにより特定の個人を識別できるものや
番号・記号・符号などの情報単体から特定の個人を識別できる「個人識別符号」を含むものを指す。
また、情報ひとつだけでは誰のものか判別できなくても、複数の情報を組み合わせることで個人を特定できる場合、
情報全体が個人情報となる。
◎特に配慮が必要な「要配慮個人情報」
個人情報の中には、公開されることで本人に不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう取り扱いに特に配慮すべき
以下の情報があり、これらの個人情報を取得する際には、原則、本人から同意を得なければならず、漏えい等がないよう
取り扱いに注意が必要となる
・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)などの障害があること
・人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴の経歴により被害を被った事実
・被害者または被告として逮捕、捜索、差し押さえ、拘留、公訴、提訴、など刑事事件に関わる手続きが行われた事実
・非行、保護処分等の少年保護事件に関する手続きが行われたことの記述などが含まれる
個人情報
◎個人情報保護法
個人情報保護法とは、個人情報を取り扱う事業者や団体に対してその情報の保護に関する規制を定めた法律で、
個人情報の不正な取り扱いや漏えいを防止し、個人のプライバシーを保護することを目的とするもの。
◎訪問介護におけるプライバシー侵害
訪問介護サービスは利用者のプライバシーに介入する業務であり、必要以上に私的領域に踏み込まず、
尊厳を傷つけないサービス提供を強く求められることを理解する。
訪問介護サービスの提供方法や情報の取り扱いをひとつ誤れば、プライバシー侵害につながる。
以下は、訪問介護においてプライバシー侵害にあたる可能性のあるケースで、自身の行動や対応を振り返り、
当てはまるものがないかを確認すること。
・ヘルパーが訪問先に訪問予定表や提供記録、事務所支給の携帯電話を置き忘れる
・サービス提供票(実績)をケアマネへFAXするつもりが番号を間違えて誤送信する
・「転倒するから」と、利用者の行動また排せつや入浴を過度に監視する
・「効率が良いから」と、いつも同じ献立の食事を提供する、また入浴時に丸洗いする
・「こちらの方が絶対良いから」とヘルパーの価値観や考えを押し付ける
・利用者の許可なく、勝手にタンスの引き出しや備品類、手紙を開けて中を見る
・利用者の許可なく、SNSやブログに写真や私生活の情報をアップする
・職場外で利用者の実名を出しながら愚痴や悩みを相談する
・利用者の要望や要求に対して「面倒な利用者」とクレーマー扱いする
◎プライバシー保護施策の「11の取り組み施策」
①訪問介護に対する利用者の権利の告示
訪問介護は、利用者と事業者の双方の意思合意により成立するもので、契約に際しては
以下の利用者の権利などを包み隠さず告げなくてはならない。
〇利用者の意思をもって契約を破棄・解約できる
〇事業者に対してサービス提供記録等の開示要求ができる権利
②情報収集時のプライバシー保護
利用者情報を収集する際には、利用者や家族が答えたくない内容の追及は避け、訪問介護計画の立案や
サービス提供に必要な内容にのみ留める。なお、アセスメントは初回以降も更新し続けるもので、
一度ですべての情報を収集する必要はない。
③帳票書類などのプライバシー情報の取り扱い
介護保険被保険者証の写しなどの帳票書類は、利用者のプライバシー・個人情報そのもので厳重管理が必要となるので、
以下の取り組みを実施する。
〇サービス提供記録や訪問予定表などの紛失や置き忘れに注意する。
〇「デスクの上に書類を置きっぱなしにしない」「外から中が見えない鍵付き書庫に保管する」などの保管ルールを
定める。
〇「基本的に帳票書類は事業所外へ持ち出さない」「やむを得ず持ち出す場合は、必要最小限の情報に留める」
などの持ち出しルールを定める。
〇パソコンのパスワード設定、ウィルス対策ソフトの導入などセキュリティシステムを強固に設定する。
〇クラウドシステム、アプリケーションなどスマートフォンを活用する場合は、パスワード設定を行う。
④サービス提供記録の言葉選び、表現方法
サービス提供記録はヘルパーだけでなく利用者や家族も見ることがある書類で、読み手のことを考えながら
作成する必要がある。「ひどい」「汚い」「勝手に」「しつこい」といったヘルパーの主観的な表現を用いず、
客観的な事実を記録するようにする。また、「家族にも言えない内緒の話」をヘルパーにしてくる場合、
プライバシー侵害にならないよう記録に残さないなどの配慮をして作成する。
⑤自己決定の原則に則ったサービス提供
訪問介護を利用する・しないを含めたサービス全体に関することや、日常でのあらゆる行動について決定するのは
利用者自身なので、訪問介護側が「お風呂に入ってください」などと強制をしてはならない。
⑥日常での情報漏えい
利用者宅外で発生しやすい日常での情報漏えい場面は以下のようなものがあり、こうした状況で安易に実名を出したり、
プライバシー情報を話したりしてはならない。
〇担当ヘルパー間の日常会話
〇街中で偶然あった近隣住民に利用者の情報を聞かれる
〇関係の薄い家族から利用者の問い合わせ
⑦スマートフォンやタブレットからの情報漏えい
訪問介護では、一般的にスマートフォンやタブレット等の機器、また電話やメール、LINEなどのアプリケーションを
使用して利用者情報を共有する。スマートフォンやタブレットには利用者のプライバシー・個人情報が保存されており、
便利だからこそ情報漏えいに対するリスク管理が必要となる。具体的な取り組みとしては、以下のようなものがある。
〇スマートフォンやタブレットの紛失や置き忘れに注意する
〇パスワードを設定する
〇公共のフリーWi-Fiに接続しない
⑧利用者宅への入室時の情報漏えい
利用者がオートロックのマンションに住んでいるケースや、キーボックス等を活用しているケースで、
ヘルパーがロックを解除する際は、周囲を確認し、暗証番号が人の目に触れないよう情報漏えいへの細心の注意が必要
となる。また、訪問介護を利用していることを他人に知られたくない方もいるので、「インターフォン越しに事業所名を
告げない(ヘルパーの名前のみ告げる)」、「制服の上から衣服を羽織り、見えないようにする」などの配慮が
必要になる。
⑨インターネット、SNSにおけるプライバシー情報の取り扱い
不特定多数の目に触れるインターネットを介した情報の発信は、プライバシー侵害のリスクが潜んでいることを
理解しておかなければならない。たとえば、
〇本人や家族の許可なく利用者または自宅が映り込んだ画像をアップする
〇SNSに利用者の実名を載せ、サービス提供時の様子を公開する
これらは、プライバシーの侵害にあたる。個人情報を載せないのはもちろんのこと、極力仕事内容には触れず
不用意な発言はつつしむこと。
⑩生活援助でのプライバシー保護
訪問介護での整理整頓時には、利用者宅の備品や私物に触れる機会があるが、利用者の許可を得ず、
手紙の内容を勝手に見たり、引出しを勝手にあけたりしてしまうとプライバシー侵害にあたる。
⑪デリケートな身体介護でのプライバシー保護
排せつ、更衣、入浴、清拭などの身体介護では、人前でデリケートゾーンをさらすという最も私的な領域に
立ち入らなければならず、疾患や障害の有無にかかわらず以下のような十分な配慮と取り組みが求められる。
〇手早く行い、肌の露出時間をできる限り少なくする
〇陰部等のデリケートゾーンにタオルをかけ、できる限り肌の露出を減らす
〇自力歩行が可能な方であってトイレに行ける場合は、できる限りドアの外で見守る
〇身体等をじろじろ観察しない
〇排せつ物のにおいに反応しない
〇利用者の行動を急かさない
◆まとめ・研修結果
プライバシー保護の取り組みと、プライバシー保護の施策について学ぶことができた。
実際の現場でのプライバシー保護は難しい場面もあるが、「自分が同じことをされたら、どう思うか」の視点を
忘れず今後も取り組んでいきたい。